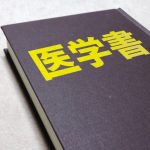近年、日本でも女性の政治参画への関心が高まっています。
しかし、女性政治家の活躍を報じるメディアの在り方には、まだ多くの課題があると感じています。
私は長年、女性の政治参画について研究してきましたが、メディアにおけるジェンダーバイアスの問題は、女性政治家の活躍を阻む大きな障壁の一つだと考えています。
本記事では、メディアが女性政治家をどのように描いているのか、その問題点と背景を分析し、改善に向けた提案を行いたいと思います。
私自身、研究者としてメディアに登場する機会も増えてきましたが、女性専門家に対する固定観念を感じることも少なくありません。
メディアのジェンダーバイアスは、政治分野に限った話ではありませんが、政治が社会に与える影響の大きさを考えると、放置できない問題だと言えるでしょう。
これから、メディアと政治の関係を、ジェンダーの視点から考えていきたいと思います。
目次
メディアが描く女性政治家像
外見や私生活への過剰な注目
メディアが女性政治家を取り上げる際、その能力や業績よりも、外見や私生活に過剰に注目する傾向があります。
例えば、女性議員の服装や髪型、恋愛・結婚、出産などが、本来の政治活動とは関係なく取り沙汰されることが少なくありません。
男性政治家の場合、外見や私生活がここまで注目されることは稀です。
「週刊文春」の分析によると、国会議員の記事のうち、容姿に言及された記事の割合は、女性議員が20.3%だったのに対し、男性議員はわずか1.1%でした(2016年調査)。
このように女性政治家の外面的な部分ばかりが注目されることで、本来評価されるべき能力や業績が正当に伝えられないという問題があります。
能力や実績より性別に焦点
メディアは、女性政治家の能力や実績を評価する際にも、性別に焦点を当てがちです。
「女性初の○○大臣」というようなフレーズを見たことがある人も多いのではないでしょうか。
もちろん、女性の活躍を称えることは大切ですが、過度に性別を強調することで、逆に女性政治家を特別視してしまう恐れがあります。
実際、2016年の国会議員の記事を分析したところ、女性議員の記事では「女性」という言葉が頻繁に使われていました(「週刊文春」調べ)。
一方、男性議員の場合、性別は注目されず、専門性や実績に焦点が当てられる傾向にあります。
このような報道姿勢は、女性政治家を「例外」扱いし、政治家としての評価を歪めてしまうでしょう。
ステレオタイプな表現の使用
メディアによる女性政治家へのバイアスは、ステレオタイプな表現にも表れています。
例えば、女性政治家を「美人議員」「セクシー政治家」などと形容したり、「母親」「主婦」といった役割を過剰に強調したりする報道が見受けられます。
こうした表現は、女性に対する固定的なイメージを助長し、女性政治家の多様性を矮小化してしまいます。
櫻井よしこ氏は、自身が「セクシー政治家」と報じられた際、「私は頭脳で勝負したい」と一蹴したエピソードが知られています(「日本の女性政治家史」)。
このように、ステレオタイプな表現は、当事者である女性政治家にとっても不快であり、その活躍を妨げる要因となっています。
メディアバイアスの背景と影響
男性中心の政治報道の慣習
なぜメディアは、女性政治家を stereotypical に描いてしまうのでしょうか。
その背景には、長年にわたって政治報道が男性中心に行われてきた慣習があると考えられます。
日本の政治の世界では、男性がリーダーシップを握ってきた歴史があります。
それゆえ、政治ジャーナリズムにおいても、男性政治家を中心に報道が行われてきました。
例えば、2000年代初頭までの新聞の政治面を見ると、ほとんどの記事が男性政治家を取り上げたものであり、女性政治家の扱いは限定的でした(「ジェンダーで読む新聞」)。
このような状況下では、女性政治家は「例外」として扱われ、ジェンダーの固定観念に基づいた報道がなされやすくなります。
女性政治家の過小評価と差別
メディアのバイアスは、女性政治家の過小評価や差別にもつながっています。
女性政治家の能力や業績が正当に評価されず、一方的に「女性だから」と決めつけられることがあるのです。
実際、2009年の衆議院議員総選挙で初当選を果たした女性議員へのインタビューでは、以下のような声が聞かれました(「ジェンダーで読む新聞」より引用)。
- 「女性だからという理由で議員の能力を疑われることがある」
- 「女性議員は役割が限定的だと思われがち」
- 「重要な政策決定の場に入れてもらえない」
このように、メディアのバイアスは女性政治家の活躍の場を狭め、不当な差別を助長する恐れがあります。
畑恵氏も、参議院議員時代、女性議員の役割が限定されている現状を指摘していました。
女性議員がその能力を十分に発揮できる環境づくりが求められています。
女性の政治参画への悪影響
さらに、メディアのジェンダーバイアスは、女性の政治参画全体に悪影響を及ぼします。
メディアが女性政治家をステレオタイプに描くことで、政治は男性の仕事という意識が強化され、女性が政治家を目指すことを躊躇させてしまうのです。
2009年の調査では、20代女性の約7割が「政治分野における男女の地位は平等ではない」と回答しています(内閣府「男女共同参画社会に関する世論調査」)。
また、「政治家は男性の仕事」というイメージを持つ人の割合も、女性の方が高い傾向にあります。
このような意識は、女性の政治参画を阻む大きな障壁となっているのです。
私自身、学生時代は政治への関心が高かったものの、女性政治家のロールモデルがほとんどいませんでした。
身近にロールモデルがいれば、より多くの女性が政治家を目指すはずです。
メディアには、多様な女性政治家の姿を伝え、女性の政治参画を後押しする役割が期待されています。
諸外国のメディアの取り組み
ジェンダー平等の視点の導入
女性政治家に対するメディアのバイアスは、日本だけの問題ではありません。
世界各国で、メディアにおけるジェンダー平等の実現に向けた取り組みが行われています。
例えば、イギリスのBBCでは、2017年に「50:50プロジェクト」を立ち上げました。
これは、番組出演者の男女比を50:50にすることを目指す取り組みです。
政治番組でも、男女同数の出演者を確保するよう努めています(BBC公式サイト)。
また、カナダのCBCでは、ジェンダーに配慮した報道ガイドラインを設けています。
ステレオタイプな表現を避け、男女のバランスに配慮するよう定めています(CBC公式サイト)。
このように、ジェンダー平等の視点を報道に取り入れることで、女性政治家に対するバイアスを減らす試みが行われているのです。
女性政治家の公正な扱い
また、諸外国のメディアでは、女性政治家を公正に扱うための工夫も見られます。
例えば、アメリカのNPRでは、政治家の呼称に関するガイドラインを設けています。
女性政治家に対しても、「Ms.」や「Sen.」など、男性と同じ敬称を使うよう定めているのです(NPR公式サイト)。
一方、ドイツの公共放送ZDFでは、選挙報道における男女平等を重視しています。
候補者の紹介では、必ず男女同数を取り上げるようにしているそうです(「諸外国の議会報道」)。
このように、女性政治家を男性と同等に扱うことで、ジェンダーによる差別を減らす取り組みが行われています。
女性記者の積極的な起用
さらに、諸外国では女性記者の積極的な起用も進んでいます。
政治報道の第一線で活躍する女性記者が増えることで、報道の多様性が高まると考えられているのです。
アメリカでは、ワシントンD.C.の記者クラブ「ワシントン政治記者協会」の会員の約40%が女性です(同協会公式サイト)。
ホワイトハウス担当の女性記者も増えており、政権に対する鋭い質問で知られるCNNのケイトラン・コリンズ記者などが注目を集めています。
また、イギリスでは、BBC政治部長のローラ・クエンスバーグ氏が、鋭い政治分析で高い評価を得ています。
2019年の総選挙では、歴代最多の女性議員が誕生したことを「新時代の幕開け」と表現し、女性の政治参画の意義を訴えました(BBC公式サイト)。
このように、女性記者が政治報道の最前線で活躍することは、メディアのジェンダーバイアス是正に向けた大きな一歩だと言えるでしょう。
日本のメディアの課題と展望
ジェンダーバイアスの認識不足
日本のメディアにおいては、ジェンダーバイアスの問題に対する認識がまだ十分とは言えません。
2018年の調査では、新聞記事の男女比は8対2、テレビの政治番組の出演者は9対1と、圧倒的に男性が多い結果となっています(東京大学情報学環・山口研究室)。
また、前述の通り、女性政治家に対するステレオタイプな表現や過剰な私生活への注目も依然として見られます。
このような状況を改善するためには、メディア関係者のジェンダー意識を高めることが不可欠です。
編集者やジャーナリストを対象としたジェンダー研修の実施など、組織的な取り組みが求められるでしょう。
ダイバーシティ推進の遅れ
また、日本のメディア業界では、ダイバーシティ推進の取り組みが遅れていると言えます。
2019年の調査では、新聞社の女性管理職の割合は7%、テレビ局は14%にとどまっています(日本新聞協会、民放連調べ)。
記者や編集者の男女比も、男性が圧倒的に多い状況が続いています。
この状況を変えていくには、女性記者の積極的な採用・登用が欠かせません。
多様な視点を報道に取り入れることで、ジェンダーバイアスのない報道が可能になるはずです。
各メディアには、ダイバーシティ推進に向けた具体的な数値目標の設定と、実現に向けた努力が求められています。
変化に向けた具体的な取り組み
とはいえ、日本のメディアにも変化の兆しが見られます。
例えば、2019年の参議院選挙では、朝日新聞と毎日新聞が候補者の氏名に「さん」付けを使うことを決めました。
男女の候補者に公平に接するための方針だと説明されています(両紙の公式サイト)。
また、一部の放送局では、女性政治家へのインタビューを増やす取り組みも始まっています。
NHKの「女性の視点で政治を問う」シリーズでは、女性議員の活動や課題を丁寧に伝えています。
2020年の特集では、コロナ禍で女性議員が直面する困難を取り上げ、議会改革の必要性を訴えました(NHKニュース)。
このように、ジェンダー平等の視点を報道に取り入れる試みは、着実に広がりつつあります。
メディア各社は、諸外国の事例も参考にしながら、より積極的にジェンダーバイアス是正に取り組むことが期待されます。
また、私たち研究者や専門家も、メディアに対してジェンダー平等の重要性を訴え続ける必要があるでしょう。
私自身、今後もジェンダーの視点からメディアと政治の関係を研究し、提言を行っていきたいと考えています。
さらに、メディアを通じて、多様な女性政治家のロールモデルを示していくことも大切です。
先に紹介した畑恵氏は、NHKのキャスターから政治家に転身し、現在は教育者として活躍しています。
このように、様々な分野で能力を発揮する女性政治家の姿を伝えることで、次世代の女性リーダーを励まし、政治参画を後押しすることができるはずです。
一方で、メディアの変革には、私たち受け手側の意識改革も欠かせません。
固定的なジェンダー観にとらわれず、批判的な視点を持ってメディア報道を読み解く。
そんなメディアリテラシーを身につけることが、私たち一人一人に求められていると思います。
まとめ
本記事では、女性政治家に対するメディアのジェンダーバイアスの実態と、その改善に向けた取り組みについて考察してきました。
メディアが女性政治家を描く際の問題点として、以下のような点が指摘できます。
- 外見や私生活への過剰な注目
- 能力や実績より性別に焦点を当てた報道
- ステレオタイプな表現の使用
こうしたバイアスは、女性政治家の過小評価や差別につながり、女性の政治参画を阻む要因となっています。
一方、諸外国のメディアでは、ジェンダー平等の視点に立った報道の工夫が見られます。
例えば、以下のような取り組みが行われています。
- ジェンダー平等の視点の導入(BBC、CBC)
- 女性政治家の公正な扱い(NPR、ZDF)
- 女性記者の積極的な起用
日本のメディアにおいても、ジェンダーバイアス是正に向けた変化の兆しが見られますが、課題はまだ多く残されています。
ジェンダーバイアスへの認識を高め、ダイバーシティを推進していくことが求められるでしょう。
同時に、私たち一人一人が、メディアリテラシーを身につけ、批判的な視点を持つことも重要です。
多様な意見や価値観を反映した報道は、民主主義の基盤を支えるものです。
メディアのジェンダーバイアスを解消し、誰もが公平に評価される社会を実現するために、私たちができることを考え、行動していく。
そんな思いを込めて、本記事の結びとしたいと思います。
読者の皆さんは、メディアの報道をどのように感じていますか?
女性政治家の活躍を伝える報道について、疑問や違和感を覚えたことはないでしょうか。
ぜひ、身近なところからメディアとジェンダーの問題について考えてみてください。
一人一人の意識が変われば、社会も変わっていく。
私はそう信じています。
男女が共に活躍する社会の実現に向けて、メディアと政治の在り方を問い続けること。
それが、研究者であり、教育者でもある私の使命だと考えています。
女性の政治参画が当たり前の時代を目指して、これからも歩みを進めていきたい。
そんな思いを、読者の皆さんと共有できれば幸いです。
最終更新日 2025年5月20日 by derevellers