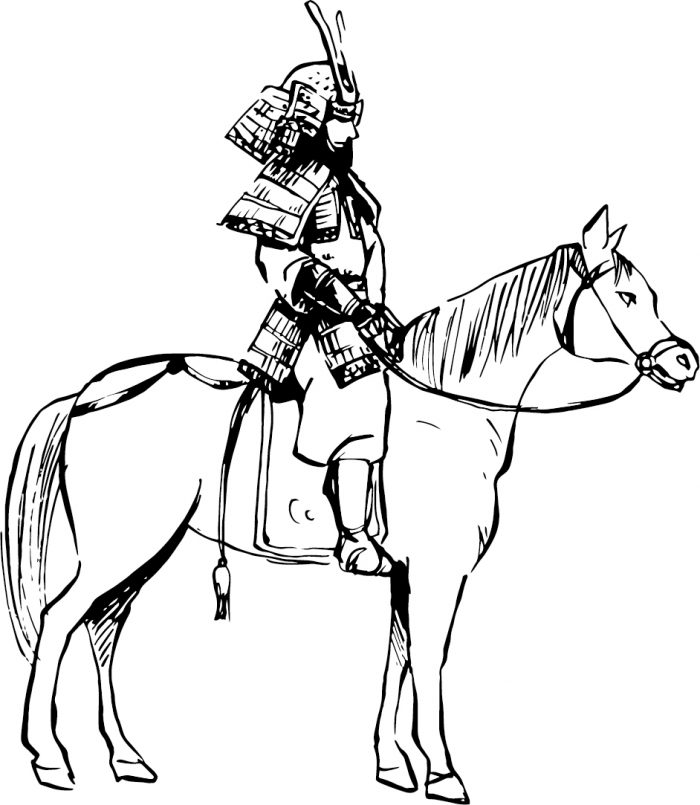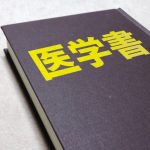歴史にあまり興味がない人でも、「前田慶次」の名前は一度は耳にしたことがあるのではないでしょうか。
「戦国一の傾奇者」という異名が有名で、近年の歴史ブームも相まって小説やマンガ、ゲームなどでより広く知られるようになりました。
前田慶次という名前自体も史実にはない通名
とは言うものの、実は前田慶次については確かな史実がほとんど存在していないという事実があります。
前田慶次という名前自体も史実にはない通名で、実際には慶次郎や宗兵衛という説や利太・利卓・利益・利治・利貞など複数あり、晩年には出家して「穀蔵院ひょっと斎」というユーモラスな名前を名乗っていたとも言われています。
生誕も天文元年や天文2年、天文10年であったり、没年も慶長10年とする説と慶長17年という説があり、父親に関しても諸説ありますが織田氏に仕えていた滝川一益の甥である滝川儀太夫益氏という説が有力で、母に関する出自や名前は全く不明ながら前田益氏の妻だったという説が強いようです。
前田性を名乗るようになったのは、実母が前田利家の兄・前田利久と再婚したためですが、いずれにせよ戦国時代の中期から江戸時代の初期に活躍した武将で、現在では豪傑で型破りなイメージがすっかり定着しています。
さて、慶次と言えば傾奇者で知られていますが、「傾奇者」とは一体どんな人のことを指すのかはあまり知られていません。
傾奇者とは、反体制的で勝手な行動をとる武士や奉公人を指した言葉で、現在でいうところの「変わり者」という意味に近いものがあります。
芸能の「歌舞伎」を連想してしまいますが、そもそも歌舞伎も偏った異様な行動や風俗を意味する「傾く」から始まったものとされているように、傾奇も歌舞伎のどちらも異端なものとして認識されていたようです。
そんな傾奇者・前田慶次には逸話がたくさんあります。
有名な「水風呂」の逸話
最も有名な話が「水風呂」で、なんとあの前田利家を陥れた話です。
人を小馬鹿にしたり軽んじて見る傾向にあった慶次は伯父・前田利家からよく注意されていました。
もちろん慶次はこれに不満を持っていたわけですが、あるとき「今までいろいろなご心配とご迷惑をおかけして申し訳ありませんでした。これからは心を入れ替えて真面目に奉公する所存です」と利家に謝罪し、「茶を一服もてなしたいので自宅にきていただきたい」と申し入れました。
これを利家は慶次が改心したと大喜びして早速慶次の家を訪れると、慶次から「今日は寒かったので、茶の前にお風呂はいかだでしょうか」と勧められます。
利家はこれを快諾して風呂場に向かいますが、慶次はちょうど良い湯加減になっているといってその場を去ってしまいました。
しかし、それを聞いて湯船に入るとお湯ではなく氷のような冷水であったため、さすがに温厚な利家も怒ってしいまい「馬鹿者に欺かれたわ、引き連れて来い」と供侍へ怒鳴りつけますが、既に慶次は国を去った後だったそうです。
しかも、利家の愛馬であった「松風」に乗って去って行ったというのですから、やはり慶次は只者ではありません。
本能寺の変の際には滝川勢の先手となって敵陣に切り込む
そんな慶次ではありましたが、天正10年の本能寺の変の際には滝川勢の先手となって敵陣に切り込み、天正12年の小牧・長久手の戦いでは阿尾城の城代となり、城の奪還に向かった神保氏張らの軍勢との戦いで活躍しました。
ところが、義理の父である前田裕幸の死によって前田家との縁がなくなったことから慶次は出奔してしまいますが、出奔後は京都で浪人生活を送りながら文化活動に精を出していたようで、数々の連歌会に出席していたことが記録されています。
そして、当時の京都には豊臣秀吉の聚楽第などもあり全国の大名や重鎮が上洛していましたが、その中でも上杉景勝の重鎮である直江兼続と意気投合し、特に親しい間柄になったと言われています。
その後直江兼続は、浪人を続ける慶次に越後から会津に移封された上杉家に仕官するように勧め、この誘いを受けて上杉家の家臣となりました。
慶長5年の関ヶ原の戦いでは直江兼続と共に従軍し、出羽の国で起こった東軍の最上義光・伊達正宗連合を相手に、慶次は見事な戦いをしたとされています。
関ヶ原の戦いで西軍が負けると、慶次の戦いぶりを見た多くの大名から誘いがありましたが、慶次は減封されて米沢に移された上杉景勝から離れることなく従うと、現在の米沢市万世町堂森で隠遁生活に入りました。
表舞台には立たずに和歌や連歌を詠むなどの悠々自適の生活を送ったとされていますが、これは、京都での浪人時代にいろいろな文化人と交流をもったことが大きく影響しています。
まとめ
豪快なイメージながらも古田織部に茶道、里村紹巴に歌を習い、弓馬などの武芸にも秀でていたなど、慶次は当時の武士としては高い教養を持っていたと言えるでしょう。
この堂森で息を引き取った慶次ですが、このように波乱に満ちた人生であり不明な点が多いことから現在では伝説的な武将となりました。
ここに紹介した経歴や逸話は数多くの文献で見ることができますが、もしかしたらさまざまな憶測がそのまま定説になっているのかもしれません。
最終更新日 2025年5月20日 by derevellers